
今回は、先日「リコマース総合研究所(以下、リコマース総研)」の記事をmerpoliでも掲載させていただいた記事の後編です。
前編は以下からご覧ください。
「リコマース総研」については、以下の記事も合わせてご覧ください。
リコマース総合研究所
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ブランド公式リユースの成功事例——多様なカテゴリーで広がる取り組みとオペレーションの工夫
與田 祐樹 リコマース総合研究所 所長(以下、與田)> 実際にユースケースとして、ブランドと一緒に取り組んだ成功事例についてお聞かせいただけますか。
野村 晃裕 Free Standard株式会社取締役(以下、野村)> 例えば、「MARGARET HOWELL」さん、「STAUB」さん、「ヤマハゴルフ」さんなど、さまざまなジャンルのブランドのサポートを行っています。それぞれのブランドごとに特徴があり、良さがあります。
與田> 服だけでなく、鍋やゴルフクラブなど幅広いカテゴリーを取り扱われていますよね。その対応範囲の広さに驚きましたが、オペレーションはどのように構築されているのでしょうか。
野村> どの領域まで展開するかは、常に模索しながら進めています。現在は、特に重点的に取り組んでいるカテゴリーが3つほどありますが、その中でもマーケット規模が大きく、安定した成長が見込める「ファッション」に最も注力しています。ただ、他の領域についても、バランスを見ながら今後広げていく予定です。
與田> 回収して消費者の手に渡るまでのプロセスには、査定やメンテナンスの工程などが含まれると思います。こうしたプロセスは、自社で独自に構築されているのでしょうか。
野村> サプライチェーンの設計・管理は自社で行っています。ただし、多岐にわたる実作業まですべて内製化するのは難しいので、多くのパートナー様の力を借りながら進めています。具体的には倉庫やクリーニング、配送など、ヒトの部分も含めてその領域に特化したアセットを持つパートナー様との連携ができることも私たちの強みです。
與田> 提供責任の一端を担うという意味でも、プロフェッショナルな人材が多く、独自のポジションを確立しているイメージです。
野村> 手間のかかる部分こそ丁寧に向き合うことが大切ですし、パートナーに対してもリスペクトを持ち、自分たちで一度やってみることを大事にしています。例えば、オフィスでスタッフ全員で査定をしてみたり、プロセスを変更した際に実際に試してみるといった取り組みを行っています。こうした実践を通じて、外部に依頼する際の単価感も含め、適切な判断ができるようになります。
RaaS事業のスケール化の鍵——オペレーション最適化と価格設定の課題
與田> 今後、こうした事例が広がることで、サーキュラーエコノミーの推進にもつながっていくと考えています。ただ、スケールさせる上では、事業運営におけるさまざまなチャレンジや課題もあるかと思います。特に、認知度の向上とオペレーションの最適化では、どちらがより大きな課題と感じていますか。
野村> どちらも重要ですが、最も大変なのはオペレーションです。オペレーションを磨くことでコストは下がりますが、プロセスが非常に多岐にわたるため、最適化が難しい部分もあります。
具体的には、査定、メンテナンス、倉庫管理、EC販売など、RaaSとしてのクオリティを維持しながら、一点ものの特性を考慮しつつ効率化する必要があります。
また、商品数が急増した際のキャパシティ管理も大きな課題です。例えば、プロジェクトが始まるタイミングや季節の変わり目には、急激に商品が増えることがあります。こうした変動に対応しながら、倉庫の規模を適切に管理し、必要に応じて拡張できる体制を整えることが求められます。このバランスを取るのが特に難しい点ですね。
與田> リユース品は、新品よりも価格を抑えなければならない一方で、オペレーションコストがかかるため、価格設定のバランスが難しそうですね。特に、商品自体の価値が高いものがターゲットになったり、品質が求められたりする点もありますね。
野村> 現在の市場では、新品価格の約4〜5割で販売されることが多いですが、それでもオペレーションコストをすべて吸収できるわけではありません。特に、ファストファッションの価格帯になると、コスト吸収が難しくなり、課題が多いのが現状です。
ただ、ユニクロさんや無印良品さんのように、自社でリユース事業を展開している企業もあります。こうした取り組みが今後さらに広がる可能性もありますね。1つ1つの工程をしっかり進めながら、必要に応じて簡素化し、全体のプロセスを効率化することも考えられます。
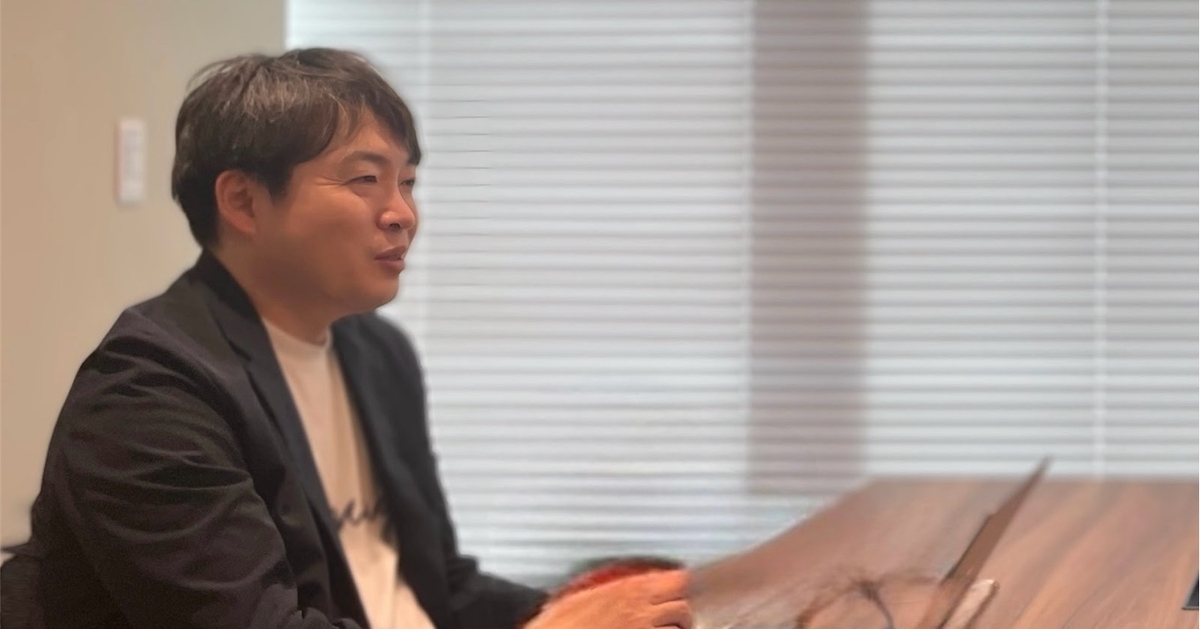
リユース市場の未来——標準化への道と政府支援の可能性
與田> 今後の市場の見通しについてお聞かせください。事業が広く浸透したと感じられるのは、どの程度の認知度に達したときでしょうか。
野村> 指標として特に具体的な数値目標を設定しているわけではありません。ただ、企業においては、ブランドリコマースの価値が伝わり経営上の重要度が高まることを目指しているので、「サステナブル活動」の側面と「事業成長」の両面から取り組む企業が増え、私たちがサポートしていない企業からも次々と事例が発信されているような状態を作りたいですね。
與田> まだRaaSやリユース事業を自社で展開していないブランドも多く、これから標準化が進む段階なのではないかと感じています。オンラインストアも、かつては導入が進んでいませんでしたが、例えばオンライン販売の比率が5%程度から始まり、10%を超えてくると「オンラインストアは当然のもの」という認識が広まりました。RaaSも、ブランドの導入率が10%を超えるあたりで大きな変化が起こるのではないでしょうか。
野村> ECが広まった流れと全く同じだと思います。ファッション業界でもECの導入当初は「ネットで服が売れるわけがない」という意見が多かったですよね。サイズが分からないなどの課題がありましたが、それでも徐々に大手ブランドが参入し、今ではほぼ全てのブランドがECを導入しています。
リユース事業も同様に、5年、10年というスパンで新しい消費のスタンダードになるサービスが生まれています。今後、ほぼ全てのブランドが公式リユースを展開する未来が確実に訪れるでしょう。それをどれだけ早く実現できるかだと思います。
與田> 政府のデータを見ても、サーキュラーエコノミーの実現に向けて、循環資源の活用や環境負荷の低減が重要課題として認識されています。こうした背景の中で、政府の支援があれば、よりスムーズに進められるのではないかと思うのですが、具体的にはどのような支援が有効だと考えますか。
野村> 欧米でリユースが強く進んだ要因の一つは、政府の介入だと思います。例えば、欧州ではリユースを促進するために規制があり、売れ残った衣類の廃棄に罰金が科される仕組みなどがあります。アメリカでも税制優遇の議論が進んでいますね。
日本では罰金の導入は日本の文化に合わないかもしれませんが、税制優遇なら実現可能性が高いのではないかと考えています。現在、DXに対しては補助金や減税措置があります。また消費者向けにはエコポイント制度などがあります。
與田> 環境省の「デコ活」では、消費者へのインセンティブ設計の在り方が議論されていますね。また、リユースが経済的なメリットにつながることで、お客さまにとってもより身近な選択肢となり、普及がさらに加速しそうですね。
野村> また、税制優遇や補助金も大事ですが、やはりお客さまからの支持を得ることは重要な視点です。一度使ってみると、その良さが分かるので、まずは多くの人に体験してもらうことが大切です。まずは消費者に広く知ってもらい、実際に利用してもらうことが鍵になりますね。
與田> 特にインフレが進む中で、コストを抑えつつ質の高い商品を求める動きが強まっていると思うので、合理的な形でリユースが受け入れられる期待は高いですよね。
野村> そう思います。豊かさというのは、経済的な側面ではお金を得ることですが、精神的な側面では選択肢が増えることが大きいと思います。新品だけでなく、リユースという選択肢が増えることで、消費者の自由度も高まると思います。
売り買いの場をメルカリが作ったことで、消費の選択肢は広がりました。家や車などの高価格帯の商品から低価格帯へのリユースの波が広がっていますが、これは人間の本質として、より自由な選択肢を求める流れなのかもしれません。
「ブランド公式」といった新しいリユースの選択肢があることは、まだ十分に知られていない部分もありますが、知っていただければ選択肢が増えることは歓迎されると思っています。

おわりに
サーキュラーエコノミーの実現は国家戦略として位置づけられ、これまでの大量生産・大量消費・大量廃棄という経済モデルから、商品寿命を延ばし、適切な量を生産しながら繰り返し利用するサーキュラーエコノミーへの転換が求められています。本記事を通じて、ブランドの公式リユースを支えるRaaSが、リユース市場の拡大に大きく貢献していることがわかりました。
特に、収集・メンテナンス・個品単位の在庫管理など、二次流通ならではのオペレーションの複雑さは、企業にとって大きな課題です。こうした中、メルカリでも「買取リクエスト」を開始し、事業者と連携することでリユース品の収集を支援する取り組みを進めています。
野村さんのお話にもあったように、リユース市場がさらに広がることで、消費者にとって新たな選択肢が生まれる未来が期待されます。リコマース総研は引き続き市場の動向を探り、その発展を後押ししていきます。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村 晃裕(Akihiro Nomura)
Free Standard株式会社 取締役。2006年ワイキューブ入社。組織人事コンサルティング事業、ブランディングコンサルティング事業などの新規事業立ち上げを行った後、2011年にリンクアンドモチベーションに入社。中小ベンチャー向け組織人事コンサルティング事業、ベンチャーインキュベーション事業、組織改善クラウド「モチベーションクラウド」事業に従事し、2020年Free Standard設立に参画。グロービス経営大学院にてMBA取得。
インタビュワー
與田 祐樹(Yuki Yoda)
リコマース総合研究所 所長。青山学院国際政治経済学部卒業。大手印刷会社系列のITベンチャーを経て、2011年にグリー株式会社入社。ソーシャルゲームやスマホゲームの開発マネジメントやプランニングを担当。2015年に株式会社ファーストリテイリングへ入社し、PMとしてユニクロアプリやジーユーオンラインストアの開発を担当。2018年2月に株式会社メルカリ入社し、US版/JP版メルカリにてProduct divisionのマネージャーを担当。その後、メルカリ経営戦略チームに参画、ディレクター Head of Recommerce。。2024年4月より現職。
藤井 彩香(Sayaka Fujii)
メルカリ経営戦略室政策企画、リコマース総合研究所研究員。2020年岐阜市役所入庁。上下水道事業部、市長公室で勤務。直近の市長公室秘書課においては、岐阜市長の出張手配、交際事務及び市政功労表彰をはじめとする各種表彰の事務に関する業務等に従事。2024年4月から2025年3月までメルカリに派遣研修中。経営戦略室政策企画に所属し、サーキュラーエコノミーへの移行におけるリユース・CEコマース推進とトレンド作りに関わる業務を担当。2024年11月には岐阜市「メルカリShops」の開設業務、2025年1月には岐阜市立則武小学校での出前授業に携わる。
