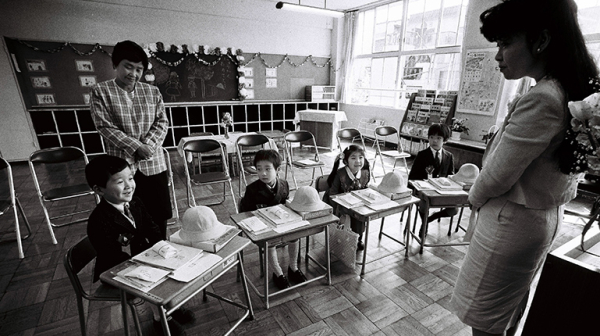「文系が寝ない理系の授業」の秘密 京大助教の母校での挑戦
「理系の授業は睡魔に襲われる」。文系高校生の「あるある」な姿に、一人の先生が立ち上がった。京都大学複合原子力科学研究所の中村秀仁助教(46)は、母校の大阪高校(大阪市東淀川区)への出張授業を通じ、文系の生徒にも理系科目へ興味を持ってもらう取り組みを続けている。その内容とは――。
「放射線に関係する単位で正しいものは? A:シーベルト B:シートベルト」
2択のクイズを出された生徒が手にするのは、スマホ。こうしたクイズができ、無料でダウンロードできるアプリをあらかじめ入れ、次々と質問に答えていく。
放射線が専門の中村助教は、2006年から学校で出張授業を実施してきた。あるとき、生徒へのアンケートの結果を見て驚いた。回答が理系の生徒ばかりで、文系はほぼゼロだった。授業中に寝ていたり、隠れてスマホを触ったり――。思い返すと、そんな生徒の姿が浮かんできた。
「スマホを使って、参加型にしたらどうか。スマホを触っていれば眠っているヒマもない」。22年、クイズ形式の参加型授業を始めた。
効果はてきめん。受講者の半分ほどは文系だったが、寝る生徒はいなくなった。授業内容について、自ら図書館で調べたり、新聞記事をスクラップしたりする生徒も現れるようになった。
手ごたえをつかんだ中村助教は、もう一歩踏み込んだ。授業内容をスケッチブックにまとめ、大阪高の近くの住民や、京都大のイベント参加者へのプレゼンテーションを生徒に持ちかけた。初めは戸惑う生徒が多かったが、慣れてくると、次第に面白がるようになった。
保護者からは「家で黙りがちだった子どもが、発表の練習を通じ、家族で会話することが増えた」「自分から進んで調べ物をしたり、ニュースを解説してくれたりするようになった」とうれしい声も届いた。
大阪高の西中聖虹さん(3年)は「初歩的なクイズから学びが大きく広がっていくのが楽しかった。科学を学ぶことは理系も文系も関係ない」、坂部偉吹さん(2年)は「これまでは授業内容をいかに答案用紙に正確に書けるかという勉強だったが、学んだことを人に伝えることで自主性が向上した」と話す。
こうした取り組みは、中村助教の名前のイニシャルにちなんで「Nプロジェクト」と名付けられており、今後も続けられる。これまでの内容や成果は8月、大阪・関西万博の会場で、生徒たちが描いたスケッチブックとともに発表される予定だ。
中村助教は「科学は本来、身近なもの。文系の人たちにも興味を持ってもらうことで、社会全体に科学への理解を広げたい」と話している。
有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。
【春トクキャンペーン】有料記事読み放題!スタンダードコースが今なら2カ月間月額100円!詳しくはこちら