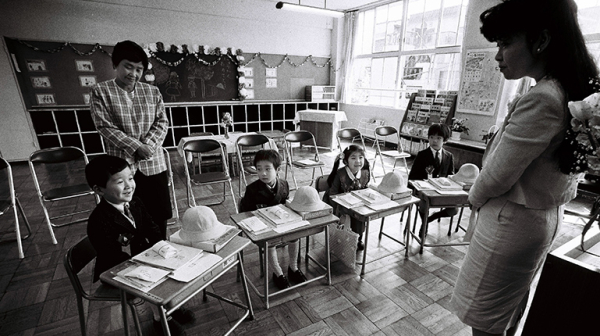選挙の偽情報規制、表現の自由と難しい線引き 収益得る仕組みも論点
現場へ! SNS選挙(4)
兵庫県知事選などを機に、国会では偽・誤情報や誹謗(ひぼう)中傷の拡散が社会問題として広く認識されるようになった。
石破茂首相(68)は1月、NHK「日曜討論」に出演した際、選挙をめぐるSNS情報の規制のあり方について問われ、「夏には東京都議選や参院選がある。それまでに一致した見解を出すことは重要だ」と語った。
2月14日、選挙運動のあり方を検討する与野党協議が国会内で開かれた。自民党の逢沢一郎・選挙制度調査会長(70)は会議の冒頭で、「偽情報が拡散し、有権者に伝わり、誹謗中傷でひどい事件が起きる。深刻な事態で放っておけない」と強調。立憲民主党の大串博志・選挙対策委員長(59)も「国会としてなにがしかの答えを出さないといけない」と応じた。
すでに公職選挙法では虚偽事項の公表に対し罰則を定める。情報流通プラットフォーム対処法にも投稿を削除できる規定がある。しかし、村上誠一郎総務相(72)は同日の衆院予算委員会で「総務省に調査権はなく、警察で調査してもらうしかない。ただ、表現の自由に抵触しないように、どこまでの範囲を取り締まれるのか」と答弁。「表現の自由」の観点から、どのような行為や情報を規制するのかの線引きは難しいと指摘した。新たな法整備については「選挙の問題は各党間で議論してもらうしかない」。
事業者の対応を問題視する声も
ただ、SNS規制には慎重な…
【春トク】締め切り迫る!記事が読み放題!スタンダードコース2カ月間月額100円!詳しくはこちら
- 【視点】
玉木代表がSNS規制に否定的なのは、単純に自身(や国民民主党)の人気がソーシャルメディアに支えられていることを考えれば当然のこととは思います。一方で、兵庫県知事選後の竹内県議の自死や、金儲けを目的とした出馬、フェイクニュースを堂々と主張した
…続きを読む