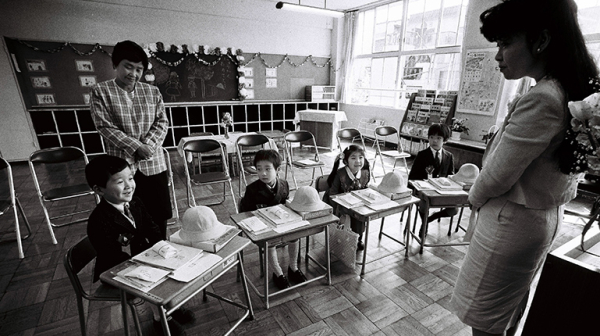時速194キロ死亡事故で「危険運転」認定 残る定義のあいまいさ
死亡事故を引き起こした時速194キロの運転を、大分地裁の裁判員裁判は「危険運転」と認定した。判決のポイントになったのは、車が進路から逸脱することなく進行できた場合でも「危険運転」として認められる場合がある、としたことだ。
どういう場合に危険運転とされるのかは、自動車運転死傷処罰法で八つの類型が定められている。その一つが「進行を制御することが困難な高速度」で車を運転し死傷事故を起こした場合だ。検察側は公判で、被告の運転がこの類型にあたると主張していた。
弁護側は「被告は直進走行できており、進路を逸脱していない」、つまり進行は制御できていたと反論していたが、判決は過去の判例も挙げて「進路から逸脱することなく進行できる場合も含まれる」という前提を示した。
その上で、194キロという速度で夜間に運転した際の状況について検討。道路にはわだち割れなど傷みがあったと推認できる▽車の揺れやハンドル操作の回数が増える▽視力低下や視野の縮小が起こる傾向がある、などと列挙。「ハンドルやブレーキの操作のわずかなミスが起こり得ることは否定できない」と指摘し「交差点を右折してきた車と衝突するなどの事故を容易に想定できる」とも述べた。
こうしたことから、194キロという速度は「わずかなミスにより車を進路から逸脱させ事故を発生させる危険性がある速度といえる」と判示。「進行を制御することが困難」という類型に当てはまり、危険運転が成立するとした。
一方、検察官の主張を認めない部分もあった。
危険運転の類型には「妨害目…
【春トクキャンペーン】有料記事読み放題!スタンダードコースが今なら2カ月間月額100円!詳しくはこちら