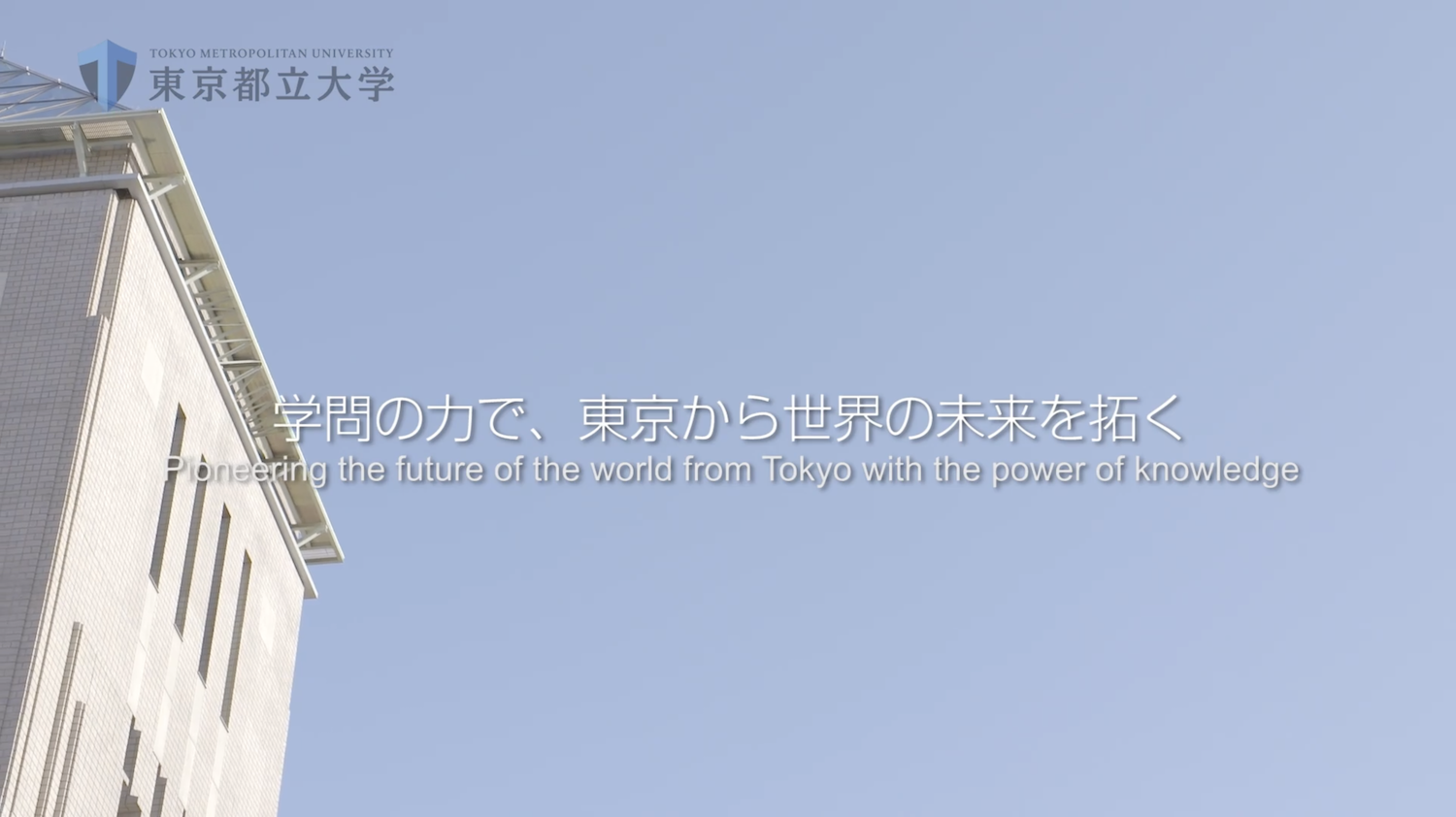■名物教授訪問@法政大学
法政大学経営学部の川島健司教授は、同大の「学生が選ぶベストティーチャー賞」を2020年度から3年連続で受賞し、殿堂入りしました。コロナ禍でのオンライン授業と、その後に再開した対面授業で、変化に応じた工夫を重ねて授業を行っています。人気の理由はどこにあるのでしょうか。どんな授業をしているのか、また会計学とはどんな学問なのか、中高生と保護者へのアドバイスも含めて聞きました。(写真=法政大学提供)
会社の決算情報を、言葉から研究
川島健司教授は会計学を専門としています。
「会計とは、会社や個人の経済活動の実態を、お金の観点から明らかにする行いや仕組みのことです。具体的には、経済活動の取引を記録・要約して決算書を作り、報告します」
会計には財務会計や管理会計、税務会計、国際会計など、いろいろな分野があり、川島教授が研究しているのは財務会計です。財務会計は、株主や債権者など会社の外の人が利用することを目的とする会計です。どのように記録・要約して決算書を作るか、誰にどのような優先順位で報告するか、報告は役に立っているのかなど、会計の実務について研究しています。
特に興味を持っているのが、会計の言葉の使用法です。会計には勘定科目とよばれる測定単位があり、それを言葉のように使って実態を表現します。ですから、会計はよく「事業の言語」と言われます。例えば、「収益」という言葉は、文脈や使う人の意図によって、「売り上げ」という意味にも「利益」(売り上げから費用を引いた差額)という意味にも使われます。場面や文脈に依存し、教科書的な定義はあっても、そこから離れた使い方をされることもあります。言葉の意味が違えば事実の認識が違ってきますから、経済活動での意思決定が誤ったものになる可能性があります。そこで、会計の言葉がどういう状況でどのように使われているのかを調査、研究しています。
教科書の書き込みを写真で提出
川島教授が法政大学の「学生が選ぶベストティーチャー賞」に初めて選出された2020年度は、新型コロナウイルスの感染が広がり、大学も翻弄された年でした。授業はすべてオンラインに切り替わり、学生は大学に来られなくなってしまいました。
「学生の不安と不満を解消し、学ぶモチベーションを高め、達成感を持ってもらうことが重要でした。そこで授業の動画を見た感想を受講生全員に提出してもらい、一覧にして、みんながコメントし合えるコミュニティーを作りました。これにより、学生同士がオンラインでつながることができました」
学生が気に入った感想にコメントしたり、疑問を学生間でやりとりしたりして、コロナ禍であっても、いやむしろコロナ禍になったことで、それまでの大教室での授業ではなかったつながりが生まれました。その結果、学生のモチベーションも上がりました。
同じ頃、60年以上前に法政大学を卒業した公認会計士の和食克雄氏から「蔵書を引き取ってもらえないか」という問い合わせがありました。届いた箱を開けてみると、その中に会計学の教科書があり、ページに書き込みがされていました。
「写真を撮って学生に見せたら、デジタル世代には新鮮だったようです。これを機に学生が教科書に書き込みをして、みんなで共有する取り組みを始めました。学生は書き込みを写真に撮って提出します。全員分を一覧にして、誰の書き込みが面白いか投票し、上位に入ったものをみんなで読むことにしました」
この取り組みによって、オンライン授業でも自分以外の受講生の気配がさらに感じられ、書き込みの内容から学ぶこともできました。学生は調べたことや考えたことを日記のように教科書に書き込み、それをみんなで共有しながら学ぶという、新しいスタイルの授業が始まりました。

「先生が100分話すなら、オンラインでいい」
ところが、コロナがいったん落ち着いた22年度に対面授業を再開すると、学生から思わぬコメントが寄せられました。2年ぶりの対面授業ですから、川島教授は話す内容を吟味し、充実した授業をしたつもりでしたが、「先生が100分話すのであればオンラインでいい」と言われたのです。
「最初はショックを受けましたが、もっともな指摘です。なぜ学生が教室に来るのか、なぜ私が話すのか、今まで当たり前だった対面授業の意味を初めて考えさせられました。すぐにシラバスを書き換え、グループディスカッションなどの対話型の授業を取り入れました」
加えて、『起業ストーリーで学ぶ会計』(中央経済社)という自著を使い、架空のデータやストーリーではなく、実在する会社の起業から株式上場への歩みを描いたノンフィクションの物語を通じて会計を臨場感をもって学べるようにしました。
同書で取り上げたのは、学生が身近に感じられる、コスメ・美容サイト「@cosme」を運営するアイスタイルという会社です。授業の最終回には、創業者の吉松徹郎氏を招き、教科書の主人公が実際に教室に現れるというサプライズも用意しました。コロナ禍を耐え忍んだ学生たちに、キャンパスで授業を受ける喜びを感じてほしい、という気持ちからでした。
「それまでの私は、とにかく自分の知識を余すところなく話すことが良い授業だとばかり考えていました。しかし私に足りなかったのは、授業に参加する学生の心情をよく知ることだったのです。コロナ禍の学生たちがそれに気づかせてくれました」

23年度からは、対面とオンラインの利点を合わせた授業を行っています。生成AI(人工知能)が普及し、文章による課題で評価することが難しくなる中、アナログの書き込みの共有をさらに重視するようになりました。授業で使う動画は、内容が同じであっても毎年作り直し、対面授業では一方的に話し続けずに学生との対話の時間を重視するなど、受講生の参画意欲と充実感を高める工夫を続けています。
経済学と経営学の違いとは?
川島教授は法政大学の付属高校出身です。吹奏楽部でオーボエとコントラバスを演奏し、約2000人の観客を前に舞台に上がりました。そのまま法政大学に進学し、学部は経営学部を選びました。
「経済学部と経営学部のどちらに行けばいいのか、とよく高校生などから聞かれますが、経営学は経済学に比べてより具体的で、身近な企業の話が出てきます。経済学は逆に具体的なものを抽象化して議論し、日常との距離がやや遠くなる傾向があります。原理を抽象的に考えるのが経済学、原理の応用を具体的に考えるのが経営学とも言えます。現場で見聞して具体的な事例から考えることが好きな人は経営学部、数学とか抽象的なゲームが好きで理論的に考えていくことが好きな人は経済学部が向いているかもしれません」

生成AIの技術が進んでいくこれからの時代、中高生はどんなことを心がければいいのでしょうか。
「作家の井上ひさしさんは著書『井上ひさしと141人の仲間たちの作文教室』の中で、『自分にしか書けないことを、だれにでもわかる文章で書く』ことが作文の秘訣だと言っています。生成AIの登場で、『自分にしか書けないこと』がより重要になっています。五感を使っていろいろなことを体験し、関心を広げて、地元の生活範囲だけではなく、地球全体の範囲で考えられるようになると良いですね」
川島教授は、高校生たちが自分で興味、関心を持って学部を選んでくれることを期待しています。
「部活動、旅行、新聞を読むといったことを通して何か驚く発見をしたり、なぜこんなことになっているのかと疑問を持ったりすることが大切です。そこから興味、関心が広がり、その先に進路が見えてくるからです。保護者は子どもにプレッシャーを与えても、なかなか思うようにはならないものです。それより、保護者自身が楽しそうに新しいことを勉強したり、誰かのために知識を使って社会還元したりする姿を見せるほうが、良い効果があるかもしれません。子ども自身が自発的に選択する力と機会を大切にしてほしいと思います」
《プロフィル》
川島健司(かわしま・けんじ)/法政大学経営学部教授。法政大学経営学部卒、一橋大学大学院商学研究科博士後期課程修了。商学博士。千葉商科大学商経学部講師を経て、2007年法政大学経営学部講師。同准教授を経て、14年から現職。15〜17年、米国カリフォルニア大学バークリー校客員研究員。法政大学高度会計人育成センターの初代センター長として公認会計士を育成。20年度から3年連続で「学生が選ぶベストティーチャー賞」に選ばれ、殿堂入り。専門は会計学。
(文=仲宇佐ゆり、写真=法政大学提供)
【写真】教科書の書き込み、一番面白いのは誰かを競う ベストティーチャー賞で殿堂入りの人気授業とは
記事のご感想
記事を気に入った方は
「いいね!」をお願いします
今後の記事の品質アップのため、人気のテーマを集計しています。
関連記事
注目コンテンツ
-
九州から未来を創造しよう! ~多分野×多様性×グローバル環境で、世界で活躍するオンリーワン人材を育成する
自然科学系から人文社会科学系、そしてデザイン系と広汎な「知」が結集する九州の雄・九州大学。同大学では「総合知で社会変...
2025/03/28
PR
-
芝浦工大が考える「新しい工学の学び」~課程制への移行で社会の変化に対応できる技術者を育成
芝浦工業大学工学部は、複雑化する産業や社会の変化に応じた柔軟な工学教育を実現するため、2024年度から学科制を課程制...
2025/02/26
PR
-
11学部を擁する総合大学としての強みを生かす。関東学院大学が分野横断的なデジタル人材を育成する「情報学部」(設置構想中)を新設
企業や自治体、地域と深く関わり合いながら学ぶ「社会連携教育」を掲げ技術力や協働力をもつ人材を育成し、社会のニーズに応...
2025/02/21
PR
インタビュー
-
「環境に優しい農薬」とは? AIやロボットを使って、何百倍もスピード開発
■名物教授訪問@公立諏訪東京理科大学 農作物を害虫、病気、雑草などから守ってくれる農薬は、現代の農業に欠かせないもの...
2025/01/25
-
-
慶應義塾大学
現代を生きる私たちと『学問のすゝめ』櫻井翔さん × 伊藤公平(慶應義塾長) 【前編】
『学問のすゝめ』刊行150周年を記念して、慶應義塾長の伊藤公平が、スペシャルゲストと対談を行いました。予測困難な現代...
2023/05/15
-
-
おすすめ動画
大学発信の動画を紹介します。
大学一覧
NEWS
教育最新ニュース
- 教育 - 朝日新聞 2025年 04月 16日
- 学ぶ機会なかった私「ただ普通になりたい」 夜間中学で踏み出す一歩 2025年 04月 16日
- 卒業式参加の不登校生徒を平均台に座らせる さいたま市立中が謝罪 2025年 04月 15日
- 養魚場のエサ高騰 幼虫を使った新飼料で救え 学生ベンチャーが開発 2025年 04月 15日
- 法人化案に抵抗の「鎖」 学術会議の総意は? 異例の総会始まる 2025年 04月 14日
Powered by 朝日新聞