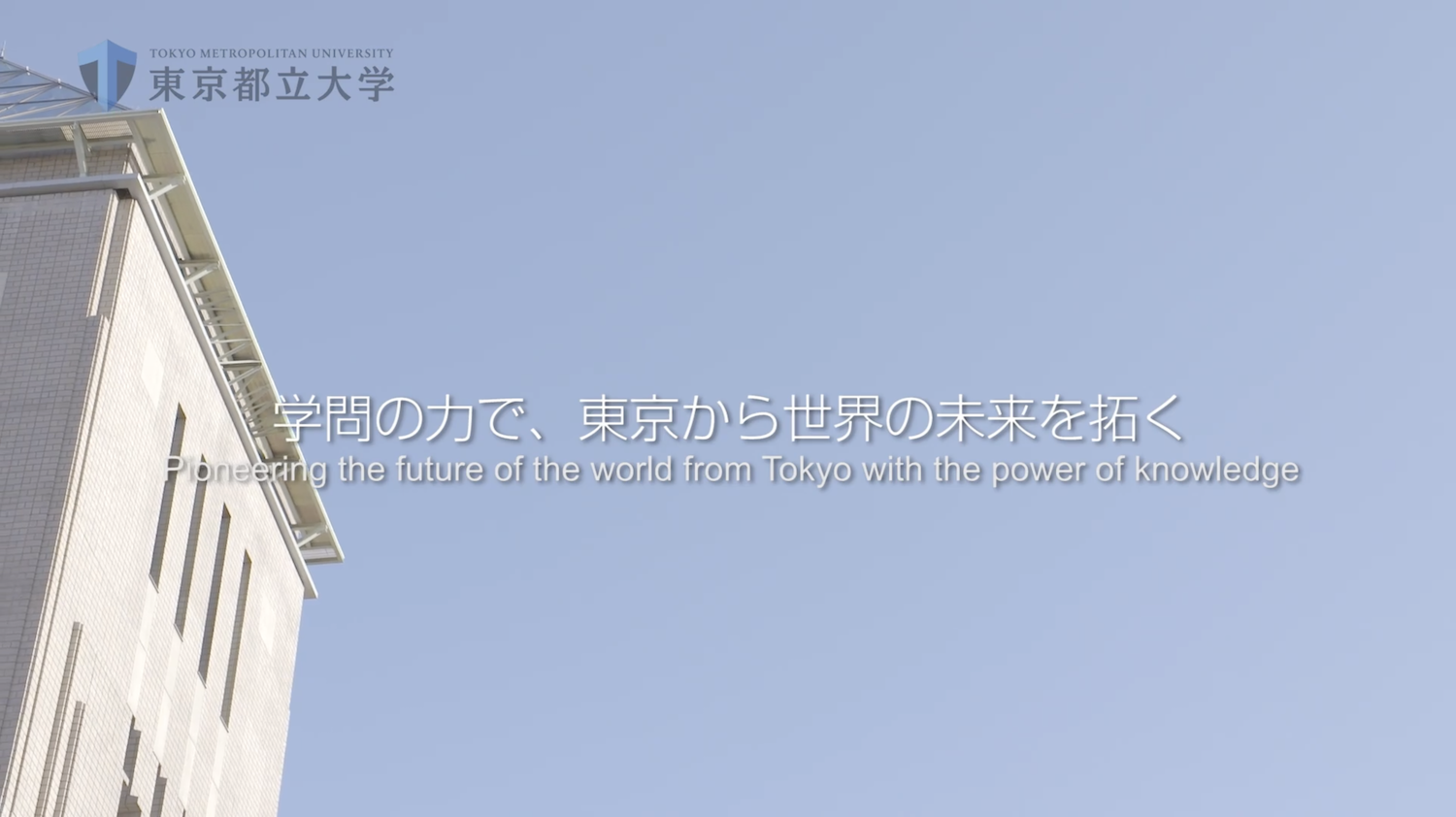■特集:多様化する年内入試
「中学受験は限られた都市部で過熱しているもので、わが子の大学受験には関係ない」と思っている人もいるかもしれません。しかし、追手門学院大学客員教授で学習塾業界誌「ルートマップマガジン」の西田浩史編集長は、中学受験経験者の増加が、近年の大学入試の変化にも影響を与えていると言います。探究学習に力を入れている高校が、進学実績を伸ばしています。特に試験方式が複雑な総合型選抜では、早めの情報収集と中高時代の探究学習が大切だとも指摘。その理由と、具体的な対策について聞きました。(写真=Getty Images)
探究学習に強い高校が躍進
西田編集長は、大学入試の変化と中学受験との関わりを、次のように説明します。
「中学受験を経験した都市部の親は、わが子の進路への意識が高い。子どもが中1の時点から、大学の年内入試を見据えた対策を始める家庭も出てきています。こうした親が増えることで、大学入試のスタートも早期化しているのでしょう。そしてこの傾向は地方にも波及してくるということを、全国の親が意識しておくべきです。年内入試、とくに総合型選抜による合格者の動向は、まだ母数が少ないので意識されにくいところがあります。しかし、これが高校の進学実績や序列に影響してきていることは間違いありません」
近年、進学実績を伸ばしている高校には、「探究学習に強い」という共通点があるようです。この傾向は私立中高一貫校でも公立高校でも同様で、これも年内入試の拡大によるものだと西田編集長は話します。
「探究学習では、グループワークやプレゼンテーションの練習ができます。これによって伸びるのが、総合型選抜で求められる、旧来の教科学習ではフォローできない力です。国語や社会などの教科でも座学による一斉授業を減らし、表現力を磨くなどの方法がとられていることが多くあります」

「不動とされてきた地方トップ校の地位も変わりつつある」と西田編集長は言います。
「トップ校に次ぐ2番手の公立高校が中高一貫校化する動きが、都市部近郊から地方にも広がっています。6年にわたる教育と大学入試の特性を理解した指導の効果で、総合型選抜の合格実績と高校のレベルが逆転する、いわゆる『下克上』が起きています」
「親力」が試されるのでは
西田編集長は「地方では、近隣にある特定の難関大学の年内入試に狙いを定めて指導を行う高校も出てきています。大学の入試方式に合わせた指導方法は、すでにかなり確立されていると言っていい」と指摘します。そしてこの現象は、学校の多い都市部で起きていることともよく似ています。新興の私立高校や2番手の進学校が、プレゼンや志望書類作成のためのツボを押さえた指導をし、年内入試で躍進している例が多くあります。

「中学受験のときに目いっぱいの偏差値で学校を選ぶと、入学後の評定平均が取りにくくなります。こうしたことや各校の指導内容を理解している親が、大学受験を見据えて、志望する中学を下方修正するケースもよく見るようになりました」
「もはや中学受験の志望校は、大学受験の年内入試を重視して選ぶ時代」と言う西田編集長。中学も高校も、可能なら入学前に、その学校の大学受験への姿勢を確認しておきたいと言います。
「一番確実なのは、学校説明会などで先生に『一般選抜以外の受験に向けた指導はありますか』『指定校推薦や総合型選抜に積極的ですか』と尋ねることです。とくに地方の進学校では一般選抜信仰が強く、共通テストを受けるよう強制されることもあると聞きます。入学してからこうした学校の方針に異を唱えるには、親の介入が必要になることもあります。総合型選抜の最新事情を見ていて強く感じるのは、これは親力(おやりょく)が非常に問われる方式であるということです。その意味で、大学受験も中学受験化してきていると言えるでしょう。将来的にはこの傾向はもっと強くなり、親子二人三脚でこそ成功する試験になるかもしれません」
早めの情報収集が必須
自分たちの頃とはまったく違う様相を呈する大学受験に、親世代はどう向き合えばいいのでしょうか。親がすべきことは、都市部でも地方でも、子どもが何歳でも変わらないと西田編集長は言います。
「子どもがすでに高校生という家庭でも、とにかく早く情報収集を始めて、できれば学部・学科まで、進路の方針を早急に絞ることです。中学受験の経験者はこの部分でスタートダッシュを決めていることが多い。地方の公立校の親御さんは、その出遅れを意識して一刻も早く動き始めることが肝心です。中1で始めても決して早すぎることはありません。もし途中で子どもの希望が変わったとしても、それは学校や学びを研究した成果だといえます。高3になってあわてるよりもずっといいことです」
この情報収集がうまくいけば、総合型選抜は都市部と地方の教育格差や体験格差を埋める逆転の一手にもなりそうです。へき地の公立高校は、体験や実績づくりの面で不利なようにも見えますが、その土地ならではの課題や自然・文化などを研究し、総合型選抜を勝ち抜く受験生も生まれています。
では、具体的な情報収集の方法はどうしたらいいのでしょうか。
「塾の無料説明会や、大学が開催している年内入試の説明会や対策講座などに参加してみることです。近隣に学校がある都市部の人は対面で、それが難しい地方の人はオンラインでも構いません。2、3校の話を聞いてみれば、大学側が何を求めているかもつかめるはず。そのうえで、わが子に足りないものや伸ばしたいものを見極めて、参考になりそうな本を複数買ってみると、押さえるべき共通点がわかってより効果的です」
西田編集長が語る最新事情を踏まえて、ここで親がすべきことをもう一度整理してみましょう。
中高生の親がすべきことはまず、とにかく総合型選抜の情報をキャッチすること。「うちの子には関係ない方式」と判断するのは、その後でも遅くありません。さらに都市部なら大学に足を運んでみること、地方なら都市部の動きが広がってくると意識しておくこと。いずれも、「一般選抜を受けてこその大学受験」「トップ校の地位は揺るがない」といった親世代の固定観念を手放して、感覚をアップデートしておくことが不可欠です。
(文=鈴木絢子)
【写真】増える総合型選抜への対策とは 「親子二人三脚がカギ」と専門家が指摘
記事のご感想
記事を気に入った方は
「いいね!」をお願いします
今後の記事の品質アップのため、人気のテーマを集計しています。
関連記事
注目コンテンツ
-
九州から未来を創造しよう! ~多分野×多様性×グローバル環境で、世界で活躍するオンリーワン人材を育成する
自然科学系から人文社会科学系、そしてデザイン系と広汎な「知」が結集する九州の雄・九州大学。同大学では「総合知で社会変...
2025/03/28
PR
-
芝浦工大が考える「新しい工学の学び」~課程制への移行で社会の変化に対応できる技術者を育成
芝浦工業大学工学部は、複雑化する産業や社会の変化に応じた柔軟な工学教育を実現するため、2024年度から学科制を課程制...
2025/02/26
PR
-
11学部を擁する総合大学としての強みを生かす。関東学院大学が分野横断的なデジタル人材を育成する「情報学部」(設置構想中)を新設
企業や自治体、地域と深く関わり合いながら学ぶ「社会連携教育」を掲げ技術力や協働力をもつ人材を育成し、社会のニーズに応...
2025/02/21
PR
調べて!編集部
-
レイクレともやんがYouTuberになった理由!大学選びは?高校生へのメッセージで名言が!?
▼ブカピ:国学院久我山入部&3P対決 ・【高校バスケ】レイクレともやん國學院久我山に初入部!デカすぎる1年生ビッグマ...
2023/05/28
-
東京理科大学
東京理科大学 Labo Scope(創域理工学部 電気電子情報工学科 木村研究室)
「宇宙ゴミを除去するための、衛星搭載用カメラの開発やロボットの自律制御を研究し、より安全な宇宙空間の実現へ」東京理科...
2024/05/15
-
横浜国立大学
多様な健康長寿社会のためのバウンダリ・スパナー・デザイン研究拠点紹介
学問境界や最先端技術と社会の境界、身体能力や文化などの境界(バウンダリ)を超え互いの営みに対する理解を促すとともにそ...
2023/05/10
おすすめ動画
大学発信の動画を紹介します。
大学一覧
NEWS
教育最新ニュース
- 教育 - 朝日新聞 2025年 04月 15日
- 卒業式参加の不登校生徒を平均台に座らせる さいたま市立中が謝罪 2025年 04月 15日
- 養魚場のエサ高騰 幼虫を使った新飼料で救え 学生ベンチャーが開発 2025年 04月 15日
- 法人化案に抵抗の「鎖」 学術会議の総意は? 異例の総会始まる 2025年 04月 14日
- 「げた箱が怖い」小1の息子 直面する「壁」に親ができること 2025年 04月 13日
Powered by 朝日新聞